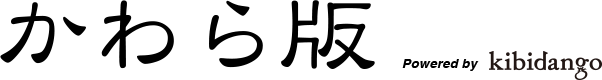クラウドファンディングと地域創生の関連性についての持論
観光・寄付に頼らない自前でのビジネス立ち上げを
人口減・働き手不足が全国で進むなか、「地域がどう生き残るか」という問いが避けられないテーマになっています。観光誘致や補助金に頼る地域施策も多くありますが、私はそこに限界を感じています。
地域が本当に強くなるには、「地域で生まれたプロダクトが、地域外の市場でも売れ続けること」が欠かせません。一時的に観光客を呼び込むことや、外部の寄付に依存するだけでは、地域経済は持続しません。大切なのは 外に向けて売れる“自前のビジネス” をつくることです。
観光・インバウンドへの依存は、地域を強くしきれない
よく地域活性の文脈で、
- おしゃれなホテルをつくる
- カフェや居酒屋を立ち上げる
- インバウンドを呼び込む
といった取り組みが語られます。もちろんこれらが悪いわけではありません。ただ、これらの多くは“訪れる人”に依存しています。景気や天候、社会情勢によって集客は大きく揺れ動き、長期的な安定を生み出しにくいのです。
観光客が「地域を好きになる」ことは素晴らしいですが、その好意が継続的な地域経済につながるわけではありません。応援の気持ちと、持続的な消費は別物だからです。
だからこそ、地域が外貨を稼ぎ、自立するためには 「商品力」×「継続販売」 の仕組みが不可欠だと考えています。
地域ではすでに“独自プロダクトの時代”が始まっている
実際、地域には素晴らしいプロダクトが増え始めています。
- クラフトビール、クラフトジン、クラフトサケ
地域の素材や水を活かしたローカルアルコールが全国的に人気になっています。 - 富山県高岡の工芸
伝統技術を活かしつつ、現代的なデザイン性の高い新商品が次々に生まれています。 - 石川県鯖江市のメガネ
世界的に評価される“産地ブランド”として、国内外のユーザーに選ばれています。
このように、各地で独自のプロダクトは増え続けています。地域には、まだ全国が知らない価値が山ほど眠っています。そして、それらが商品となり、地域外へ売れ始めている——これは地域創生の大きなヒントです。
Kibidangoが挑む“受注生産型クラウドファンディング”という仕組み
こうした地域プロダクトを、より持続的に広げていくために、私は Kibidangoで「受注生産型クラウドファンディング」 を始めようと考えています。
受注生産型クラウドファンディングとは?
イメージとしては、包丁や伝統工芸品などを対象にした、次のような仕組みです。
- 「10個注文が貯まったら発注します」
- 「30本予約が入ったら製造します」
一定数の予約を条件に、製造をスタートする受注生産型のクラウドファンディングサイトです。顧客は注文してもすぐには届きませんが、その代わりに「作り手と一緒につくる」「完成を待つ」という体験も含めて楽しむことができます。
顧客側のメリット
- すぐ届かない代わりに、特別感のあるプロダクトを予約できる
- 作り手の想いやストーリーを知ったうえで購入できる
作り手(メーカー)側のメリット
- 発注数が確定してから生産できる
- 在庫リスクがゼロ になる
- 生産コストを下げやすい
- 小規模工房や伝統工芸の職人でも挑戦しやすい
包丁、伝統工芸品、クラフト飲料、ローカルブランド…。ロット確定後に生産できる仕組みは、地域の小さな事業者ほど大きな力になります。地域が抱える資金・人手・在庫の問題を、クラウドファンディングの仕組みで解決するアプローチと言えるでしょう。
地域が挑戦し、東京(外部)が応援する未来
私は、「地域が挑戦して、東京(外部)が応援する」、そんな未来がもっとあっていいと思っています。
都市部は人口も消費力も情報発信力も大きい。一方で地域には、まだ知られていない価値がたくさんあります。その価値がクラウドファンディングのような仕組みを通じて“外の市場”につながるなら、日本全体にとってもプラスです。
地域内だけで完結させる必要はありません。地域の価値は、外部の力を借りながら育てていけばいい。クラウドファンディングは、その接点をつくるための便利なインフラになり得ます。
地域を盛り上げるのは「地元民」だけとは限らない
もう一つ強調したいのは、地域を盛り上げるのは必ずしもその地域の住民だけでなくて良いということです。
近年は地方移住者やUターン・Iターンの人たちが、地域の人たちと協力しながら新しい挑戦を始める事例が増えています。移住者が持つ新しい視点や経験が、地域にとって大きな推進力になることも少なくありません。
そして、こうした“外からの挑戦者”が動きやすい環境をつくるのに、クラウドファンディングは非常に相性が良いと感じています。
- 地域の技術・素材
- 移住者のアイデア
- 外部の支援者
これらが交わることで、まったく新しい地域プロダクトが生まれる可能性が広がります。クラウドファンディングは、その出会いと挑戦を形にする「場」になり得ます。
寄付より「購入」が地域を強くする
地域向けクラウドファンディングというと寄付型が注目されがちですが、私は 購入型こそが地域自立の本質 だと考えています。
寄付は続きません。しかし購入は、商品価値があれば継続します。応援の気持ちだけでなく、「対価を払ってでも欲しい」と思えるプロダクトを増やすことが、地域の持続的な収益につながります。
つまり、地域の未来を支えるのは 寄付ではなく、売れ続けるプロダクト なのです。
まとめ:地域創生の鍵は外貨を獲得する“プロダクトの力”
地域の未来を切り開くのは、観光でも補助金でもありません。地域で生み出された商品が、地域外で継続的に売れ続けることだと考えています。
クラウドファンディングは、地域にとってその第一歩を踏み出すための最適なツールです。
- 地域だからこそ作れる価値を形にする
- 地域が挑戦し、外部が応援する関係をつくる
- 受注生産で在庫リスクなく挑戦できる
- 新しい移住者や外部人材の挑戦も後押しできる
こうした循環で地域を強くするお手伝いをしていきたいと思っています。“売れ続ける仕組み”をつくる地域が、これからの日本の未来を支えていくのではないかと強く感じています。